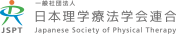人体解剖学実習に関するアンケート調査報告書
人体解剖学実習に関するアンケート調査報告書
このたび、(一社)日本基礎理学療法学会から、「人体解剖学実習に関するアンケート調査」を実施しましたのでご報告いたします。
●調査概要
1.目的
2016年度に(公社)日本理学療法士協会(日本理学療法士学会 解剖学実習検討ワーキンググループ)で実施されたアンケート調査から約8年の年月が経過した。また、2021年に(一社)日本理学療法学会連合が設立され、学会の見解を取りまとめるにあたり現況の把握が必要である。そこで、人体解剖学実習の理学療法士養成校での教育上における実態を明らかにする目的でアンケート調査を実施した。
2.調査期間
令和6年5月7日(月)~令和6年6月30日(金)
3.調査対象
理学療法養成施設理学療法学科(専攻)責任者
発送数 278件
4.調査方法
Google Formを使用したアンケートシステム(インターネット)
5.回収状況
回収件数:178件 有効回答率:64%
6.実施体制
本アンケートは、Google Formを使用し、日本基礎理学療法学会理事長の下、人体解剖学実習検討委員会が実施した。
| 藤澤 宏幸 | 日本基礎理学療法学会 理事長 |
| 河上 敬介 | 日本基礎理学療法学会 副理事長 |
| 荒川 高光 | 日本基礎理学療法学会 人体解剖学実習検討委員会 委員長 |
| 榊間 春利 | 日本基礎理学療法学会 人体解剖学実習検討委員会 委員 |
| 浦川 将 | 日本基礎理学療法学会 人体解剖学実習検討委員会 委員 |
| 江玉 睦明 | 日本基礎理学療法学会 人体解剖学実習検討委員会 委員 |
| 坂本 淳哉 | 日本基礎理学療法学会 人体解剖学実習検討委員会 委員 |
| 菊池 真 | 日本基礎理学療法学会 人体解剖学実習検討委員会 委員 |
| 堀 紀代美 | 日本基礎理学療法学会 人体解剖学実習検討委員会 委員 |
| 成田 大一 | 日本基礎理学療法学会 人体解剖学実習検討委員会 委員 |
●調査結果の概要
1.人体解剖学実習の実施状況
・2016年実施分(前回)と比較し、対象となった教育機関で大学が増加した(大学51.7%、専門学校48.3%、2016年:大学41.7%、専門学校58.3%)。
・ご遺体を用いた実習(剖出を含む/含まない、見学含む)は全体の67%で実施されており、前回(70%)とほぼ同じであった。
2.実習環境
・実習回数は「1回」23.6%、「2回」21.1%、「3-5回」21.1%であり、実習回数を「不充分」としたのは33.3%であった。前回と異なり、不充分であると回答した自由記述回答の中に「同一法人内における実習時間調整のため」という意見があった。
・実施年次を適切でないという回答が12.9%あり、前回(4%)よりも増加した。適切でないと回答したもののなかに自由記述として「4年生(or4年次)でもう一度実施できるとよい」という意見が複数あった。
3.倫理教育と交流
・実習前オリエンテーションの実施は99.2%であり、その内容は「生命倫理」39.6%。「献体制度」37.9%、「死体解剖保存法」19.6%が中心であった。
・慰霊祭参加は教員41.1%、学生16.3%にとどまり、献体登録者との交流は教員82.9%、学生95.2%が「交流なし」と回答した。
4.実習の必要性と継続性
・ご遺体を用いた実習を「続けるべき」との回答は85.5%であり、前回と同様高い値を示した。
・実施に関する不安として「解剖学教室教員の退職による継続困難」24.6%、「指導者不足」14.9%、「教員研修体制の不備」18.0%が挙げられた。
●まとめ
理学療法士養成教育における人体解剖学実習は、7割近くの施設でご遺体を用いた形で実施されており、教育的意義は広く認識されていた。実習年次は実習回数は一定の水準に達している一方で、前回と異なり、学修が進んだ時期、臨床実習を経験した後にもう一度実習を行ったほうがよいという意見が出た。学生数の割り当て、実習機会の不足、受け入れ環境の制約、教員養成や法的整備の課題が明らかとなった。
●今後
本委員会は、本調査結果を基盤に、理学療法士養成校における人体解剖学実習の適正は在り方を検討する。解剖学教育に関わる理学療法士教員の数は増加しているが、医学部歯学部解剖学教室に負担をかけることを最小限にしながら、安心して解剖学実習を実施できる環境を整えるために、さらに解剖学教育へかかわる優秀な人材を育成する必要がある。また、解剖学実習の在り方、社会に受け入れられる実習内容を含め、コンセンサスを得られるよう検討していく必要がある。
以下のPDFよりご覧ください。
アンケート結果(報告書概要)
アンケート結果(報告書)